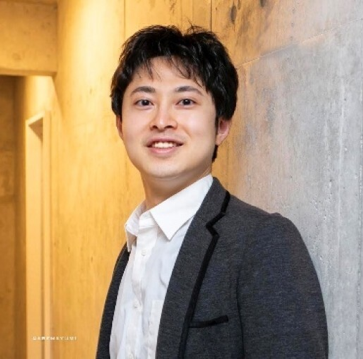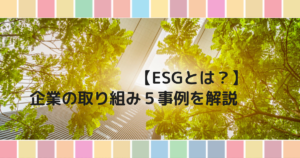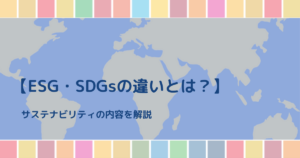SDGsが広く浸透すると同時に、「エシカル消費」という言葉も広まってきました。近年、エシカル消費の考え方は急速に広がり、日本でも意識が高まりつつあります。そのため、消費者だけでなく企業もエシカル消費を推進するように企業努力が求められるようになりました。今回は、そのエシカル消費について、企業事例も含めて解説したいと思います。
エシカル消費とは
意味
「エシカル(ethical)」とは、「倫理的」という意味で、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動のことを意味します。環境問題や社会問題などが課題視されている現在では、消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者に協力しながら消費活動を行う必要が提唱されてきました。
消費者庁の捉え方
消費者庁は「エシカル消費」の普及啓発活動を推進しており、2015年5月から2年間にわたり「倫理的調査研究会」を開催し、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動「倫理的消費(エシカル消費)」の普及に向けて幅広い調査や議論を行っています。研究会での議論を踏まえ、様々な主体と連携を図りながら、普及・啓発の取組を実施しており、国策として推進されていることが伺えます。
具体的にどんな活動か?
では、一体どんな活動が「エシカル消費」なのでしょうか?
配慮の対象ごとに紹介していきます。
<人を対象にする場合>
障碍者支援につながる商品、コロナ渦などで打撃を受けている事業者・生産者の商品
<社会を対象にする場合>
フェアトレード商品、寄付付きの商品、フードバンク
<環境を対象にする場合>
エコ商品、リサイクル製品、資源保護などに関する認証がある商品、エコバッグの利用
<地域を対象にする場合>
地産地消、被災地産品、伝統工芸品
ESG経営との関連;企業側が取り組む意味

ESG経営とエシカル消費にはSDGs(持続可能な開発目標)の目標12「つくる責任・つかう責任」の点で関連があります。
「つくる責任・つかう責任」のターゲット(目標達成の要件)として、企業に対しては、生産・サプライチェーンにおける食品ロスの減少(12.3)や廃棄物の発生防止、削減、再生利用(12.5)などを求めています。企業にとって、SDGsの目標達成に向けての活動は、ESG経営の推進においても欠かせません。そのため、エシカル消費も重要な観点になります。
消費者側の視点
企業がエシカル消費を推進するには、消費者のことも知ることが必要です。消費者にとってエシカル消費はどのように見えているのでしょうか。消費者庁、電通の調査によれば以下のことが明らかになっています。
<消費者庁の調査>
*対象エリア:日本全国
*対象者条件:16~65歳の一般消費者
*サンプル数:2803サンプル( ※日本の人口構成にあわせて、地域×性年代で割付)
参照:「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書
「あなたは、エシカル消費につながる商品・サービスを、通常の商品・サービスよりどの程度なら割高であっても購入しますか。」という質問に対する回答から明らかになったのは、多くの人がエシカル消費につながる商品・サービスを購入する意欲があることです。回答者のエシカル商品・サービスへの購入金額は、通常の商品・サービスと同額である場合が最も多いものの、おおむね25%~30%割高でも購入する意向が示されています。
この結果は、消費者がエシカルな選択肢に対して価値を見出しており、価格差があってもエシカル商品・サービスの選択を優先する傾向があることを示しています。エシカル消費の重要性が広まり、人々が個々の消費行動が社会や環境に与える影響を考えるようになった結果、価格よりもエシカル性が重視される傾向が浮かび上がっています。
この情報は、エシカル消費を促進するための戦略やマーケティングの展開に役立つことが期待されます。消費者は価格だけでなく、商品やサービスが社会的な価値を持ち、持続可能性や倫理に配慮されているかどうかも重視しています。企業やブランドは、エシカル消費者の需要に応えるために、商品・サービスの持続可能性や社会的責任に焦点を当てることが重要です。
<電通の調査(抜粋)>
*対象エリア: 日本全国
*対象者条件: 10~70 代の男女
*サンプル数: 性年代別に各 125 人ずつ、計 1,000 人を人口構成比でウエイトバック集計
消費者の半数以上が、「エシカルな商品・サービスの提供は企業のイメージ向上につながる」と考えていることが明らかになりました。
エシカルな取り組みを既に行っている業界で、消費者に強い印象を与えているのは、食品(38.1%)、自動車(23.4%)、日用品(21.3%)です。しかし、業界ごとの現状の取り組みに対する認識と期待値との間には大きなギャップがあり、電力・火力・水道、金融、旅行業界では今後の取り組みに対する期待が高まっています。
消費者にとって、エシカルな商品を購入する条件は「価格」と「商品のメリット」への納得感です。エシカル消費を促進するためには、適正な価格設定と根拠のある説明が重要です。
これらの結果は、企業がエシカルな取り組みを強化することが重要であり、消費者の要望に応えるためには価格と商品の魅力をバランス良く提供する必要があることを示しています。また、今後は電力・火力・水道、金融、旅行業界においてもエシカルな取り組みへの注目が高まることが予測されます。
企業事例
スターバックス

出典:https://www.starbucks.co.jp
アメリカのスターバックス社は、2004年に国際環境NGOの協力のもと持続可能な調達のガイドライン「C.A.F.E.プラクティス」を公表しました。このガイドラインには、安全で公正かつ人道的な労働環境を促進する措置として、「農園で働く人々の権利保護」、「賃金や福利厚生」、「雇用慣行」、「労働時間」、「保護具の使用」、「医療や教育へのアクセス」などに関する基準が定められています。
こうしたエシカルなコーヒー調達を、2015年4月には提供するコーヒーのうち99%について達成。4大陸20カ国以上のコーヒー生産者約100万人の生活環境に対する良い変化と、膨大な数のコーヒーの木を守ることにつながったと報告されています。このようなエシカルな活動に対し、コーヒーを愛する顧客から多くの共感を得られ、さらなる購買意欲の向上につなげられているようです。
インディテックス(ZARA)

出典:https://www.inditex.com/itxcomweb/en/home
ファッションブランド「ZARA」を擁するスペインのインディテックス社は、サステイナビリティに対する取り組みについて、緊急性のある課題と位置づけています。その解決のために、環境面での取り組みでは2022年に電力の100%を再生可能エネルギーから得ること、2023年にはすべての顧客に対してプラスチックの使用を100%控えることとし、さらに2040年にはネットゼロ(温室効果ガスの排出をゼロにする)を段階的な目標として掲げています。
セブンイレブン

多くの人が利用するコンビニ業界の一角であるセブンイレブンでは、食品ロス削減のためのエシカルプロジェクトを2020年から展開しています。販売期限が近いおにぎりやお弁当などの商品に緑色のシールが貼られ、その商品を購入すると消費者には会計に使用できるポイントがたまる仕組みで、食品ロス問題の認知度を高めることにも貢献しています。また、セブン&アイグループでは、2030年までに食品ロス半減という目標も掲げており、エシカル消費に力を入れています。
まとめ
- エシカル消費とは、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。
- エシカル消費の具体例には、障碍者支援商品、フェアトレード消費、リサイクル商品、被災地産品などがある。
- 調査によれば、多くの人が、エシカル消費につながる商品・サービスは多少割高であっても購入することがわかる。
- 企業は、ESG経営の一環として「サプライチェーンにおける食品ロスの減少」、「再生利用」等の推進を図るべきである。